はじめに
「走行距離課税」の導入が本格的に議論されており、X(旧Twitter)上では反発と懸念の声が急増中です。ガソリン税の暫定税率廃止を巡る恒久財源確保の一環として浮上したこの構想が、地方住民や物流業者に深刻な影響を及ぼす可能性が指摘されています。
メリットと課題の整理
| 項目 | メリット | 課題・懸念 |
|---|---|---|
| 税収公平性 | 運転距離に応じた公平な負担が可能に | 車種関係なく負担が増大 |
| 対象拡大 | EVにも課税が可能 | 地方・物流への負担増 |
| インフラ整備 | 財源の安定供給が期待 | プライバシー侵害・監視懸念 |
| EV普及支援 | ガソリン税依存からの脱却 | 制度設計の技術的・制度的課題 |
背景と導入の狙い
- 導入の背景:電動化の進行により、ガソリン税収が年約1兆円規模で減少しており、持続可能な税収確保の方法として「走行距離課税」が注目されている。
- 導入の狙い:ガソリン車・EVを問わず、走行距離に応じた公平な負担を可能とする制度を構築し、インフラ整備などの財源を確保する狙い。
- 現状:2025年6月時点では制度は検討段階にあり、正式導入の時期や形は未決定。
広がる反応
SNSでは導入に対し怒りや懸念の声が止まらず、トレンド入りするなど大きな話題になっています。以下、一部の声を紹介します。
- 「地方では車が生活必需。走行距離課税なんて死ねってこと?」
— 田舎在住ユーザー - 「物流業にトドメを刺すような政策…」
- 「意味が分からない。まず車への負担を軽くしろ」
- 「走れば走るほど罰金かよ…」
- 「プライバシー面も心配。監視社会への一歩では」
— 政治関係者や政策批評を行うユーザー
まとめ
走行距離課税は、日本の自動車税制を見直す中で、ガソリン税減少に伴う新たな財源として検討される注目の制度ですが、大きな反発も生んでいます。制度の公平性や効果性だけでなく、地方や物流業界への影響、さらには個人のプライバシーに関わる問題も含めて慎重な議論が不可欠です。今後の制度設計や国会での議論、政府の説明責任にも強い関心が寄せられています。最新情報は引き続きチェックしていきましょう。

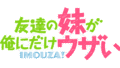

コメント